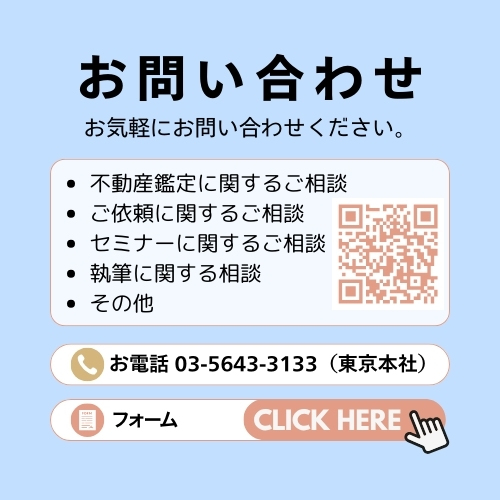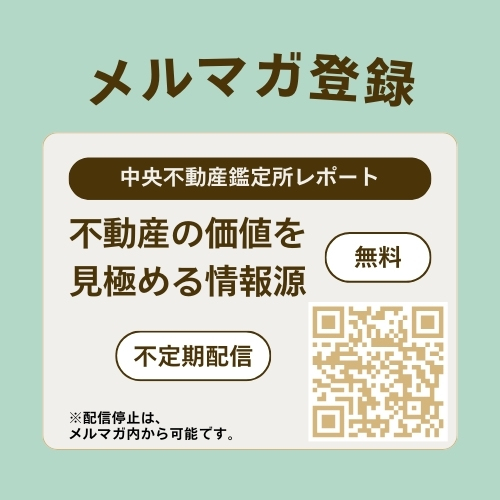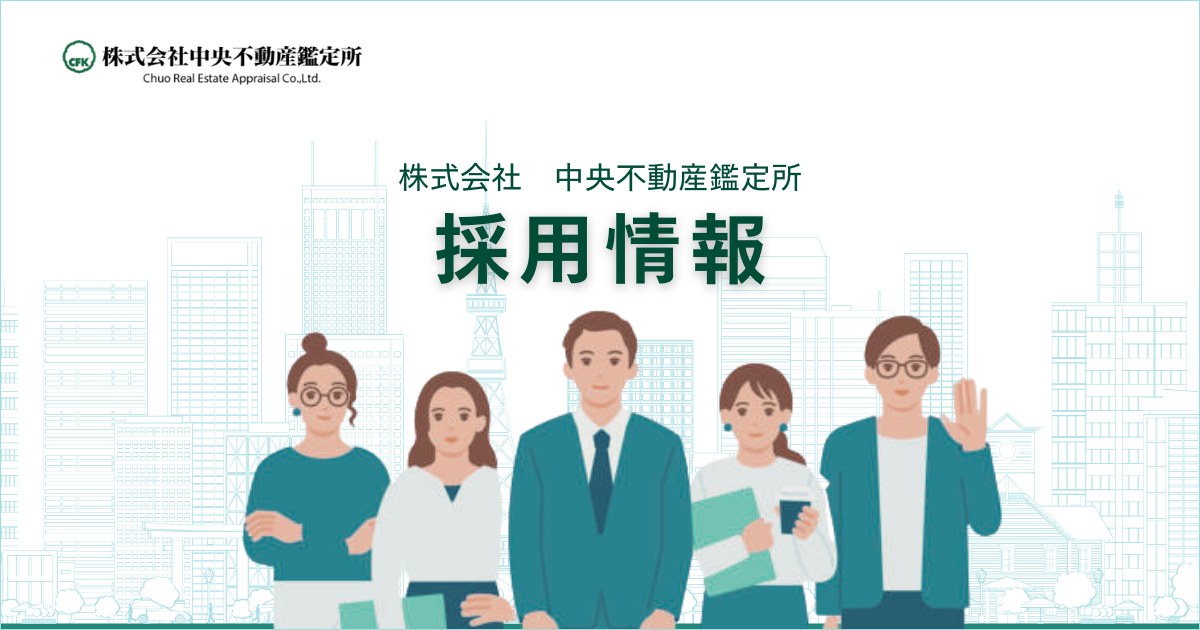地震に対して安全であるように構造物を設計する方法を耐震設計法といい、昭和56年6月1日施行の改正建築基準法に基づく現行の耐震設計法については、それ以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれている。新耐震基準では、頻発する中小地震(概ね震度5以下)に対しては建物に被害を生じさせない(1次設計)ように、稀に発生する大地震(概ね震度6以上)に対しては建物を倒壊させない(2次設計)ことを目標として設計するように義務づけている。
これまで建築基準法等における耐震設計基準は、大地震を契機に逐次改定されてきたが、「兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)」により新耐震基準に適合した建物の優位性が立証されている。不動産の鑑定評価でも建物の構造が新耐震基準に基づくものであるかどうかの確認は重要である。
なお、昭和56年以前の建物であっても超高層ビルなどは、学識経験者等による特別の審査(評定)を受けることになっており、新耐震基準以上の耐震性性能が確保されている。