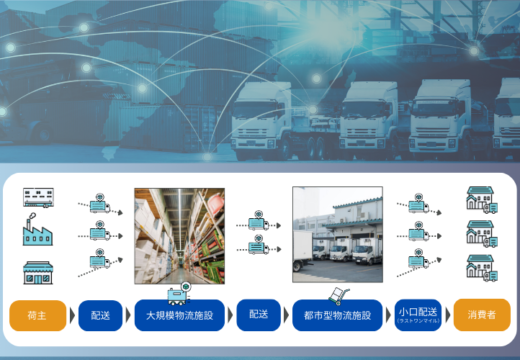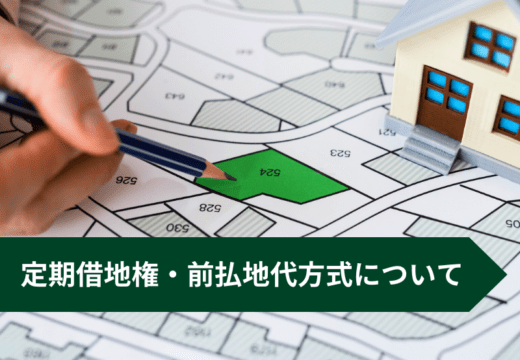最高裁判決のサマリー
原告である相続人の上告趣意書の詳細が不明ですが、最高裁の判決を流れに沿って大まかにみてみます。
| 本件は、審査請求人らが、相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、一部の土地及び建物の価額は、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をしたのに対し、請求人らが原処分の全部の取消しを求めた事案である。 |
→ 相続財産について、相続人は、通達に基づく原則である路線価方式で評価したところ、国税当局は、例外規定である財産評価基本通達総則6項により不動産鑑定評価による評価を行い、これは相続税法第22条に反すると訴えたようです。
判決文では、事実関係の認定の記載がありますが、すでに記載したとおりなので省略します。
| 原審は、上記事実関係等の下において、本件各不動産の価額については、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、本件各鑑定評価額は本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを基礎とする本件各更正処分は適法であり、これを前提とする本件各賦課決定処分も適法であるとした。所論は、原審の上記判断には相続税法22条等の法令の解釈適用を誤った違法があるというものである。 |
→ 下級審の判決の要旨と上告の争点です。
| 相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。
そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。 そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。 |
→ 相続税法の時価は、客観的交換価値をいうとしており、これまで見てきた見解と変わりません。その上で評価通達は、国税庁が各税務署の職務を指揮するための通達に過ぎないとしています。さらに国民への法的効力を有するわけではないとし、これは、相続財産の評価額(本件では1,273,000千円)は、客観的な交換価値を上回らない限り相続税法22条に反しないので、評価通達による価額(334,000千円)を上回ったとしても法に反しないとしています。原告は、通達評価の絶対性を主張したかったのですが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎない、と否定されたと解釈します。
| 他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。
そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。 もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。 |
→ まず、最初に、通達による評価は広く行われており、特定の者の財産評価に例外規定を適用することは、客観的時価を上回らなくても、合理的な理由がない限り、平等原則に違反するとの原則論を示しています。
ついで、評価通達による評価が、税負担の公平に反する場合には、合理的理由があるとし、例外規定の適用を認める判断をしています。原則と例外を示して次は当てはめになります。
| これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。 |
→ これは大変重要な判断といえます。既述の国税不服審判所の審理で、課税当局の主張として「著しい価額の乖離」が上げられていましたが、最高裁は、評価通達価額334,000千円は、鑑定評価額1,273,000千円に比べて価格差が大きいものの、価格差が大きなことだけでは例外規定(鑑定評価額)を採用するべき事情はないとの判断を示しました。
逆に言えば、通達評価額より、鑑定評価額が低い場合でも特段の事情がなければ認められないということになり、節税目的で、通達評価額より低額の鑑定評価を取得してもそれだけでは(より低廉な課税価格は)認められない可能性があるということです。
| もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。
そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。 |
→ 本件への当てはめです。相続人が節税効果の意図をもって不動産の購入と借入を行ったと認定しています。これらの一連の行為が特別な事情に該当するのかどうかを次に検討します。
| そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。 以上によれば、本件各更正処分において、札幌南税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。 |
→ 本件の相続人のように節税の為の特別な能力や資力を持たない納税者や節税を意図しない納税者との比較において、公平の観点から事情があるもの(例外規定=鑑定評価額を採用するべき)と認定しました。
以上の判断は、国税不服審判所の裁決と同様の考え方であり、税の公平性を踏襲したものといえると思います。