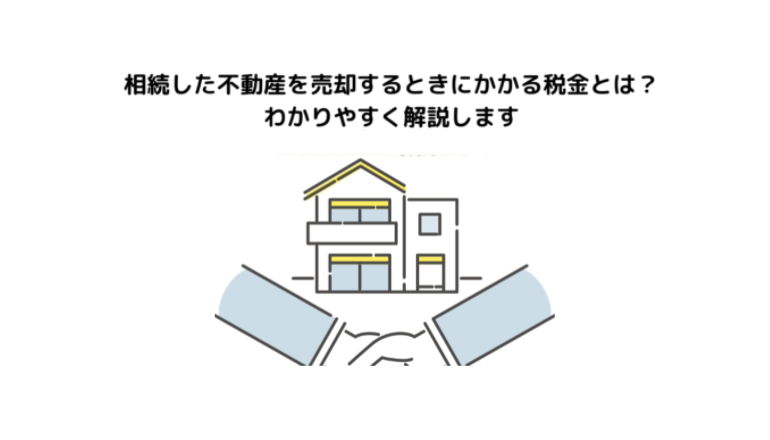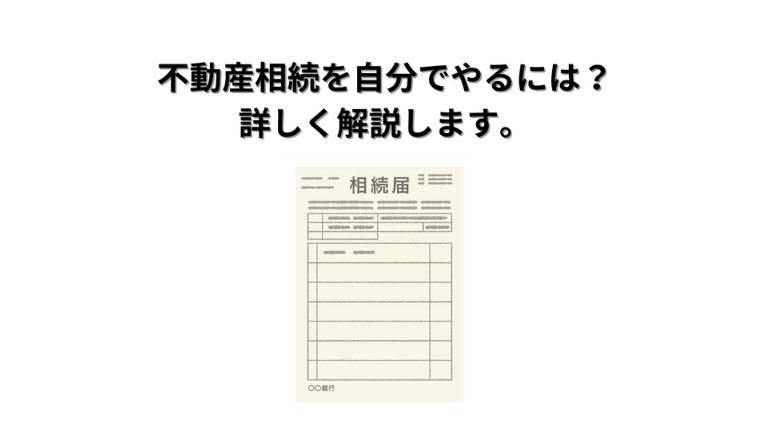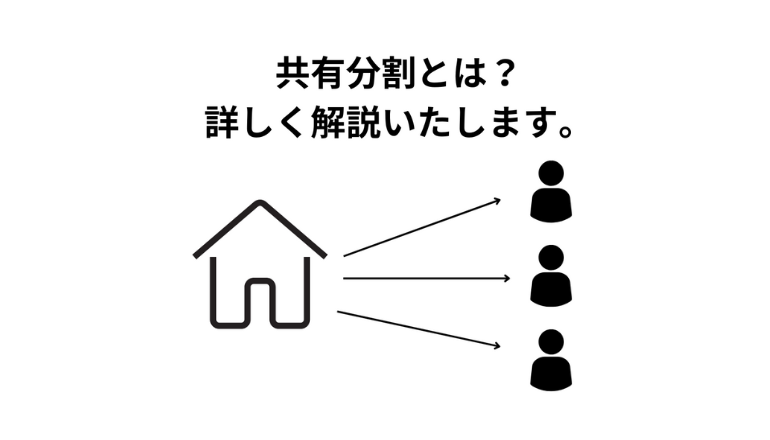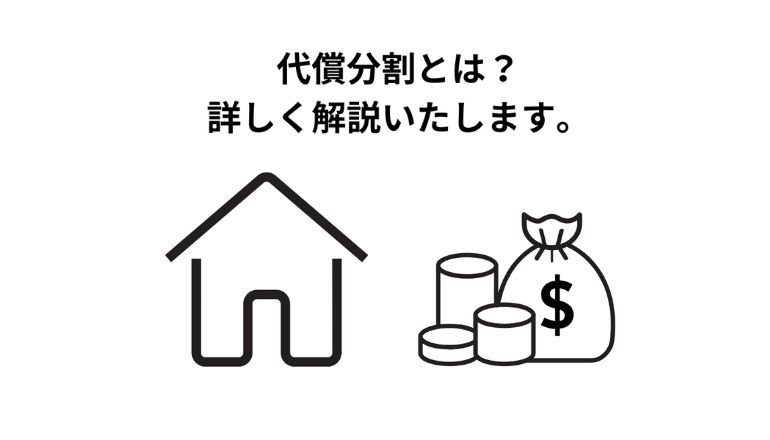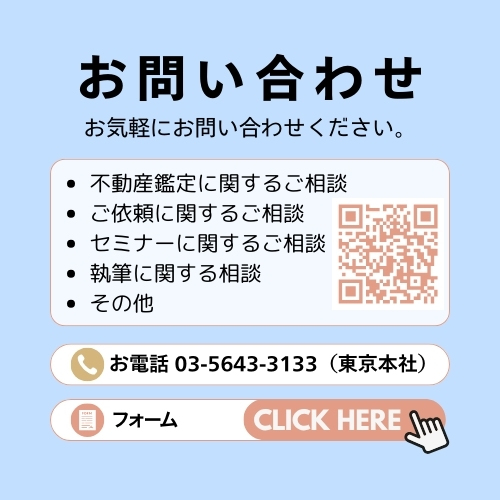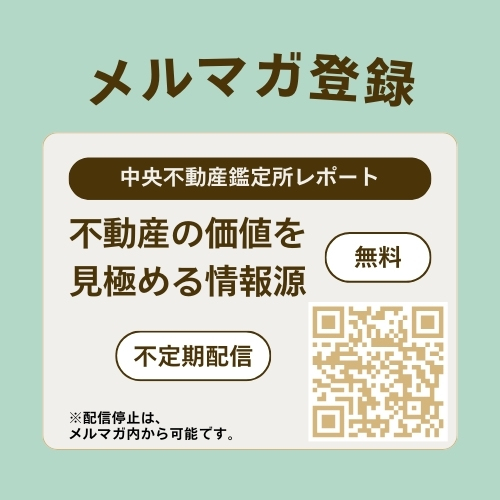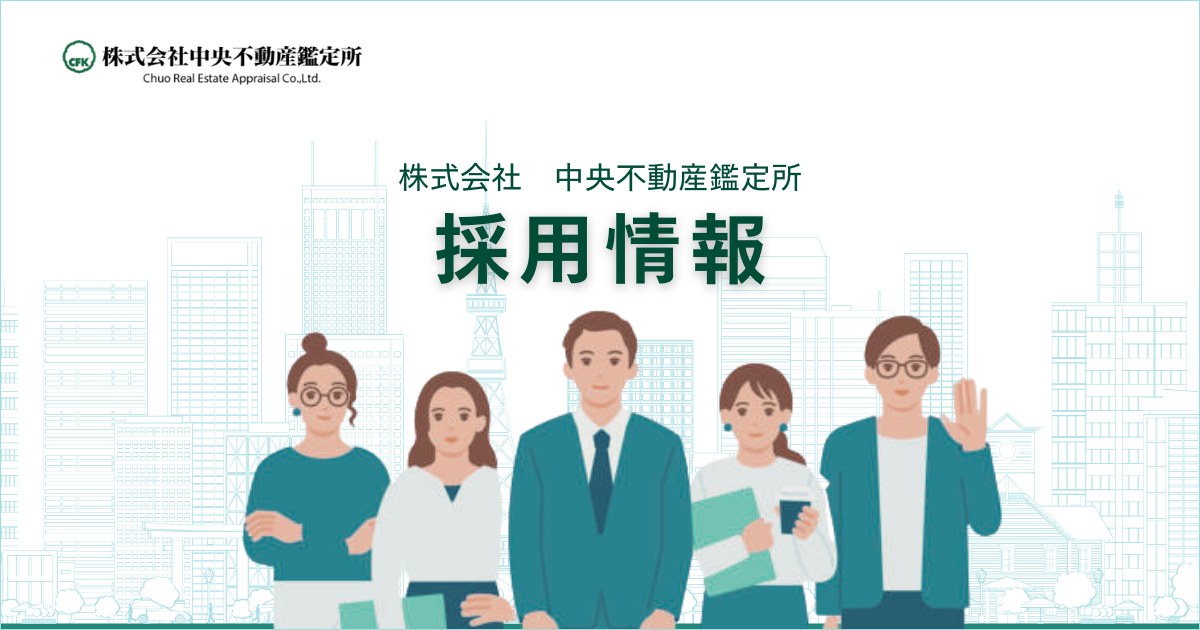相続した不動産を売却する際には、避けて通れないのが「税金」の問題です。
相続税や譲渡所得税をはじめ、売却に伴ってかかる各種税金、控除・特例の有無によって、実際の手取り額は大きく変わってきます。
本記事では、「相続不動産を売却したときにかかる税金」について、初心者にもわかりやすく解説します。税負担を軽減し、後悔のない不動産売却を行うためのポイントを押さえておきましょう。
譲渡所得税とは?仕組みと計算方法
相続した不動産を売却すると、「譲渡所得税」が発生します。これは、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 各種控除
取得費には、被相続人がその不動産を購入した際の金額やリフォーム代などが含まれます。譲渡費用には、不動産会社への仲介手数料、測量費、解体費などが該当します。
所有期間による税率の違い
- 短期譲渡所得(5年以下):所得税30%+住民税9%=計39.63%
- 長期譲渡所得(5年超):所得税15%+住民税5%+復興特別所得税=計20.315%
※相続の場合、被相続人が所有していた期間も通算されます。
売却時には、譲渡所得税のほかにも次のような税金がかかります。
- 印紙税:売買契約書の金額に応じて数千円~数万円
- 登録免許税:相続登記や所有権移転登記に必要。不動産の固定資産評価額に基づいて課税
- 住民税・復興特別所得税:譲渡益に応じて課税
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。売却前に登記を済ませることは必須です。
印紙税

出典:国税庁HP「タックスアンサーNo.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」より抜粋
登録免許税
不動産の売買や相続などで名義変更する際には、「所有権移転登記」が必要です。
この登記は、不動産の所有者を正式に変更するためのもので、法務局で行います。そして、この登記の際に国に納める税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、登記手続きを行う法務局で納付します。多くの場合は現金で納めますが、納税額が3万円以下であれば、収入印紙での支払いも可能です。
手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士への報酬の中に登録免許税の金額も含まれており、まとめて支払うのが一般的です。
登録免許税の金額は、不動産の「固定資産税評価額」をもとに計算されます。計算式は以下のとおりです:
固定資産税評価額 × 2.0%
土地と建物それぞれに対してこの計算が行われ、算出された金額が登録免許税として課税されます。
たとえば、土地の固定資産税評価額が1,999万9,900円であれば、これに2.0%をかけると399,998円になります。ただし、登録免許税は1,000円未満が切り捨てられるため、実際の納税額は399,000円となります。
このように、登録免許税は不動産取引において見落としがちな費用の一つですが、登記を正しく行うためには必ず発生する重要な費用です。あらかじめ金額を把握しておくことで、売却時の費用計画がスムーズになります。
これ以外にも契約や登記に関わるさまざまな税金や費用がかかります。
事前に把握しておくことで、手取り金額の見通しが立ちやすくなります。
不明点があれば、税理士や不動産会社に相談しながら進めるのがおすすめです。
控除や特例を活用して税金対策を
相続空き家の3,000万円特別控除とは?
相続した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
適用条件
相続した実家(空き家)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の特別控除の特例」があります。適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
① 売主が相続人であること
- 売却した人が、相続または遺贈によって空き家およびその敷地を取得した相続人であること(包括受遺者を含む)。
② 売却の対象が以下のいずれかであること
- 相続した空き家、または空き家+敷地を売却
- 空き家を取り壊した後に、その敷地のみを売却
- 上記以外で、耐震改修または解体を行ってから売却(※令和6年以降の譲渡に限る)
③ 建物・土地の利用状況に関する条件
以下のすべてを満たす必要があります:
- 相続から売却(または取壊し)までの間に、
- 事業用、賃貸用、居住用として使われていないこと
- 売却時点で一定の耐震基準を満たしていること、または翌年2月15日までに
- 耐震改修が完了している
- または解体済みであること
- 解体した場合、その後の土地が建物の敷地として使用されていないこと
④ 売却期限と金額
- 相続開始から 3年を経過する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が 1億円以下であること
※他の相続人と分割して売却した場合も、全員分の売却代金の合計で1億円以下である必要があります。
⑤ 他の特例と併用していないこと
- たとえば、「取得費加算の特例」や「収用等による特別控除」など、他の譲渡所得の特例と併用不可
⑥ 同じ家・土地について、以前この特例を使っていないこと
⑦ 「特別な関係のある人」に売却していないこと
- 特別な関係とは以下を含みます:
- 親子、夫婦
- 生計を一にする親族
- 同居している親族
- 内縁関係の人
- 売却後にその家で同居する予定の人
- 特殊な関係のある法人 など
補足
- 特例の適用後、条件を満たさなくなった場合(たとえば、他の相続人が追加で売却し、総額が1億円を超えたなど)は、4ヶ月以内に修正申告と納税が必要になります。
条件を満たせば大幅な節税が可能なため、早めの確認が大切です。
取得費加算の特例で譲渡所得を圧縮する
相続財産を売却する場合、相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が利用できます。
適用条件:
(1) 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2) その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3) その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
引用:国税庁HP
どれくらいお得になる?(具体例)
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 売却価格:5,000万円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡にかかった費用:100万円
- 相続税:800万円(うち600万円を加算できる)
この特例を使わない場合: 譲渡所得 = 5,000万円 -(1,000万円+100万円)= 3,900万円
特例を使った場合: 譲渡所得 = 5,000万円 -(1,000万円+100万円+600万円)= 3,300万円
⇒ 課税対象が600万円も減ることで、譲渡所得税の負担も大きく軽減できます。
■ 注意しておきたいポイント
- 他の特例(例:相続空き家の3,000万円控除)と併用できません。どちらが有利かを比較して選びましょう。
- 特例を適用するためには、相続税の申告書や評価証明書などの証拠書類が必要です。
- 売却後、確定申告で譲渡所得の計算を行い、特例を適用する旨を申告する必要があります。
マイホーム特例との違いにも注意
相続空き家の特例とは異なり、「マイホーム特例」は本人が住んでいた住宅を売却した際に適用されます。譲渡所得から最大3,000万円を控除できますが、適用条件や対象となる不動産が異なるため、混同しないようにしましょう。
相続不動産を売却する際の実務的な注意点
「取得費が不明な場合」はどうする?
相続した不動産の購入時の金額(取得費)が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として使えます。ただし、被相続人の資料が残っている場合は、修繕費・登記費用なども含めて正確な取得費を再計算できることがあります。
「共有名義」の不動産は注意が必要
相続不動産が複数人の共有名義になっている場合、すべての相続人の合意が必要です。売却の意志が一致しないと売却が難航するため、事前に話し合いや分割協議を行うことが重要です。
▶︎相続した不動産をどう分ける?揉めないための分割方法を解説します。
まとめ
相続した不動産の売却には、相続税や譲渡所得税をはじめとした複数の税金が関係します。しかし、「相続空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」などを正しく活用すれば、税負担を大幅に軽減することが可能です。
また、相続登記の義務化や売却のタイミング、感情的な整理など、法律面・税務面以外にも注意すべき点があります。
不安がある方は、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より安心・安全な手続きを進めることができるでしょう。
▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?