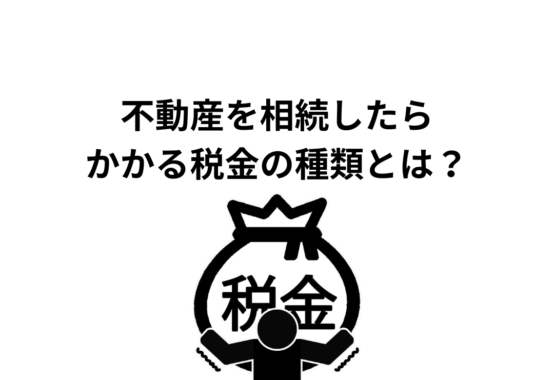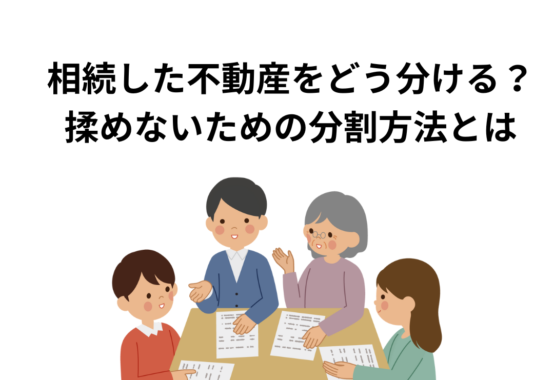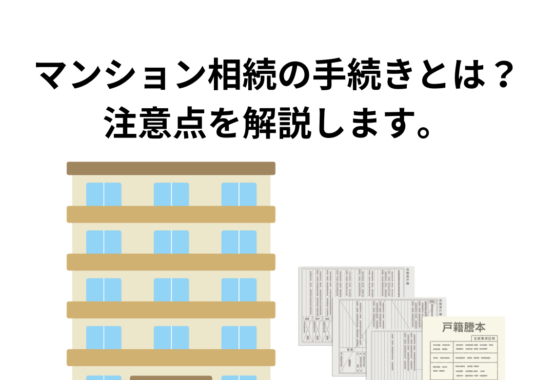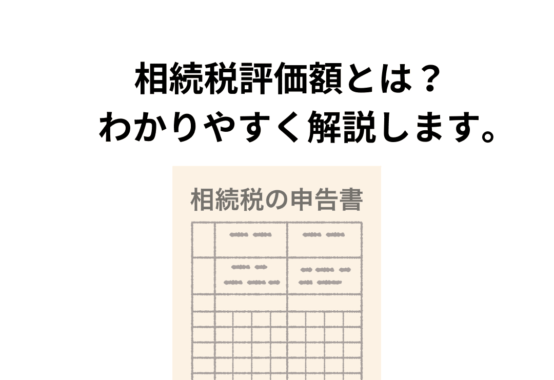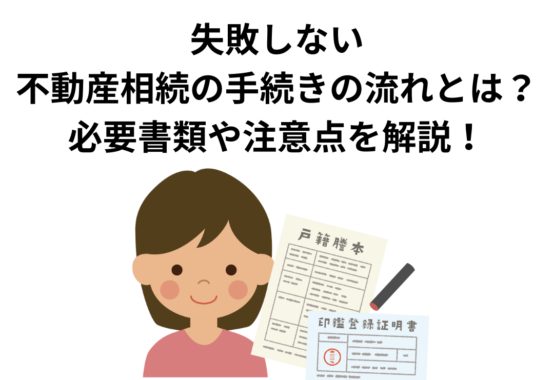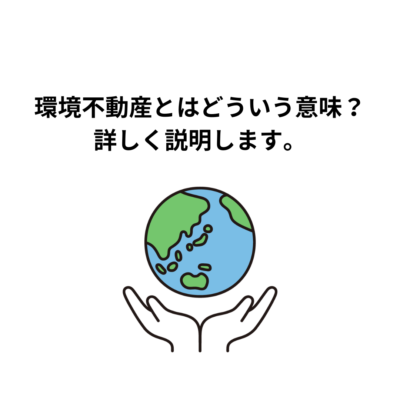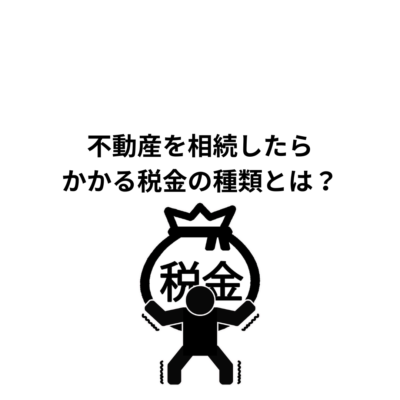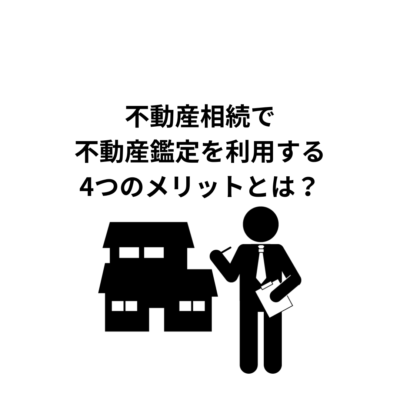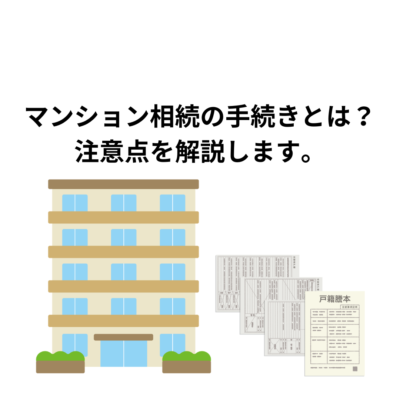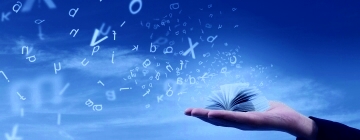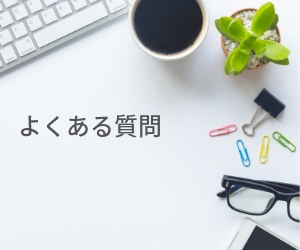タワーマンション節税とは?
近年、相続税対策として「タワーマンション」を活用する手法が広く注目を集めていました。市場価格と相続税評価額の大きな乖離を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できるとして、多くの富裕層がこの手法を活用してきました。しかし、この「タワマン節税」に関する税制が見直されることで、今後は従来のような節税効果を得ることが難しくなりそうです。この記事では、改正内容のポイントやその背景、今後の相続対策における新たな選択肢についてわかりやすく解説します。
タワマン節税の概要:なぜ節税が可能だったのか?
不動産の相続税評価額は、土地部分は基本的に国税庁が発表する「路線価」を、建物部分は市区町村が算出する「固定資産税評価額」をもとに計算されます。そのため、市場流通価額と比較すると、不動産の相続税評価額は土地部分が時価の約8割程度に、建物部分は時価の約5割から7割程度になるとされています。
たとえば、1億5,000万円の財産を現金という形で相続する場合、相続税評価額は時価と同じ1億5,000万円となります。しかし、土地4,500万円、建物1億500万円のマンションを相続した場合、相続税評価額は土地3,600万円、建物6,300万円となり、合計で9,900万円となります。結果として現金よりも不動産で相続した方が相続税評価額を低く抑えることができます。
さらに、タワーマンションの場合、高層階であればあるほど眺望が良く、需要が高いため市場価格が上昇する傾向があります。しかし、マンション1棟につき設定される路線価は1つだけのため、階層にかかわらず、床面積が同じ部屋であれば土地部分の相続税評価額は同額となります。また、建物部分も高層階と低層階で相続税評価額に大きな差はありません。
このような理由から、高層階のマンションであればあるほど、市場価格と相続税評価額の差が広がり、相続税の負担を軽減する効果が大きくなるのです。
富裕層に注目された理由①:不動産評価額と税負担の乖離
タワーマンションが富裕層から特に注目されたのは、不動産評価額と実際の税負担に乖離が生じる仕組みに主因があります。市場価格が高い物件ほど、その価格に比べて相続税評価額が低くなる可能性があり、これにより高額な相続財産を合法的に圧縮できると考えられたためです。
特に高層階のタワーマンションでは、市場価格が低層階に比べて大幅に高い一方で、相続税評価額には階数による大きな差が反映されず、税負担におけるメリットが生じやすい状況でした。また、2012年以降、不動産価格の上昇や相続税控除額の減少などの背景もあり、富裕層からの関心が一層高まりました。
富裕層に注目された理由②:従来の小規模宅地等の特例と利用条件
タワーマンション節税の一部を支えてきたのが「小規模宅地等の特例」です。この特例は、一定の要件を満たす宅地に対して相続税負担を軽減する制度で、特に土地面積が200㎡以下の場合には、大幅な評価減が認められるケースがあります。これにより、タワーマンションの土地部分についてもこの特例が適用され、相続税の負担を大きく減らすことができる仕組みでした。
なお、本特例の適用を受けるには、被相続人が居住や事業に使用していた土地であることや、相続後も一定期間その状態が継続することなど、いくつかの条件を満たす必要があります。この特例がタワーマンション節税の容易さをさらに高め、富裕層からの人気を集める要因のひとつとなっていました。
2024年の税制改正に影響を与えた課題
国税庁は、令和6年(2024年)1月1日以降に相続・贈与で取得した区分所有形態のマンション評価額の計算ルールを変更すると発表しました。
タワーマンション節税を巡っては、従来からいくつかの課題が指摘されてきました。その主なポイントは、公平性の欠如にあります。市場価格が高いにもかかわらず、税負担が低く抑えられる状況は資産規模の大きな富裕層に有利であるとされ、結果として税負担の不平等が拡大しているとの批判がありました。
さらに、タワーマンションの節税効果を狙った購入が相次ぐことで、一部の地域では不動産価格の高騰にも繋がっているといわれていました。これらの問題から、不動産評価額と実際の市場価格との乖離を是正し、公平性を向上させるための税制改正が必要と判断され、2024年には新たなルールが導入されることとなりました。
相続税評価額の引き上げ:具体的ルール変更内容
改正後、タワマンの相続税評価額は「土地部分の評価」と「部屋ごとの市場価値」の適正化を重視して算出されます。具体的には、これまで均一的に評価されていた土地部分の配分が見直され、高層階ほど相応の評価額が割り当てられるようになります。また、評価額が市場価格の6割以上となる新ルールが適用されることで、相続税額が従来よりも大幅に増加する可能性があります。このルールにより、高層階を選択する際の節税効果が著しく低下する点が注目されています。
評価乖離率とは?新たな指標の詳細
新たな評価基準の中核となるのが「評価乖離率」です。この指標は、タワーマンションにおける相続税評価額を市場価格とのバランスの中で再評価するために導入されました。特に、タワマンの高層階ほど市場価格が高騰する一方で評価額が低く抑えられる不均衡を是正するのが目的です。評価乖離率の設定により、タワマン高層階の相続税評価額はこれまでより引き上げられ、低層階との差が減少することが予測されます。
「評価乖離率」は、マンションの築年数や総階数などをもとに求めます。
「評価乖離率」の計算方法は、以下のとおりです。
評価乖離率=-A+B+C-D+3.220
マンションの築年数×0.033 (※築年数1年未満は1年として計算)
マンションの総階÷33×0.239 (※総階数÷33が1.0を超える場合は1.0で計算)
評価対象となる部屋の所在階×0.018 (※地階は0として計算)
敷地持分狭小度(※)×1.195 (※敷地利用権の面積÷専有面積)
評価乖離率が求められた場合、これをもとに「1 ÷ 評価乖離率」で評価水準を算出し、その結果に応じて補正後の相続税評価額が計算されます。評価水準と計算式は以下のように定められています。
評価水準と補正後の計算式
評価水準が0.6未満の場合相続税評価額 = 財産評価基本通達による相続税評価額 × 評価乖離率 × 0.6
評価水準が0.6以上1以下の場合補正なし(財産評価基本通達による相続税評価額そのまま)。
評価水準が1を超える場合相続税評価額 = 財産評価基本通達による相続税評価額 × 評価乖離率
※参考:国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」
たとえば、評価乖離率が1.67倍を超えると、評価水準が0.6を下回り、相続税評価額が増額されることになります。一方で、評価水準が1を超える場合は、調整によって相続税評価額が減額されるケースもあります。
築年数・階数など、マンションごとの違いに対応
2024年の改正では、さらに「築年数」「階数」「立地条件」など、タワーマンション固有の要素も新評価基準に反映されることになります。これにより、新築かつ高層階の物件が改正の影響を受けやすくなる一方で、築年数が古いマンションは若干の緩和が期待されます。また、低層階や地方都市のタワマンといった条件の物件に関しては、従来の評価方法に比べて大きな影響を受けにくいとされています。この点により、物件選びの重要性が一層高まることとなります。
まとめ
最近の税制改正により、タワーマンションを活用した相続税対策が難しくなりつつありますが、不動産は依然として現金や株式よりも相続税評価額が低くなる特性を持っています。そのため、引き続き節税の手段として有効です。ただし、2024年以降は相続税評価額の見直しが進むことで、より高度な知識と計画が必要になります。今後は、不動産を活用した節税対策として、アパートや商業施設への投資など、多角的な方法を検討することが重要です。また、非課税枠を活用した生前贈与や、資産の分散投資といった他の手段も組み合わせることで、節税の可能性をさらに広げることができます。これらの新たなアプローチを活かすためには、税理士などの専門家に相談し、自身の資産状況や家族構成に合った最適な方法を選ぶことが成功への鍵となるでしょう。
不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?
相続税と最高裁判決及び国税不服審判所の裁決 ~ 最新判例より