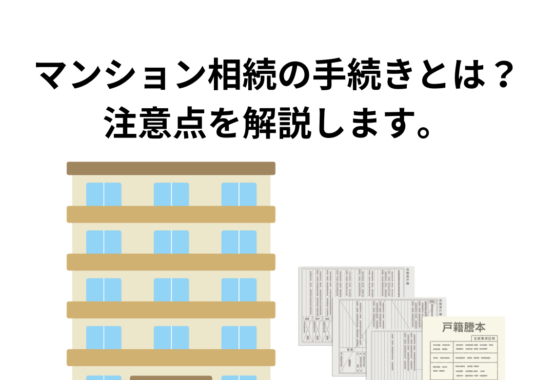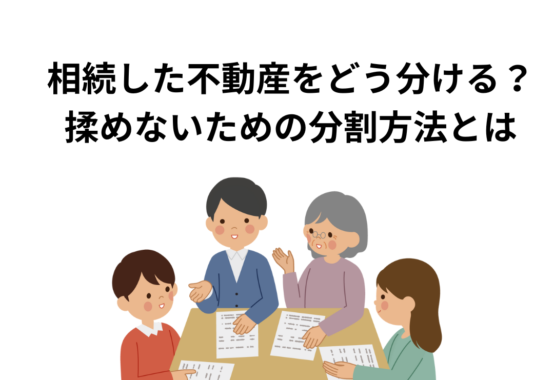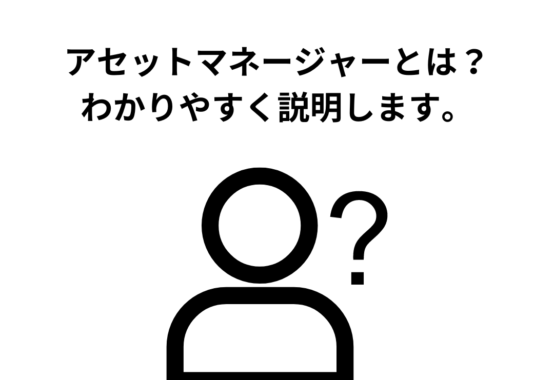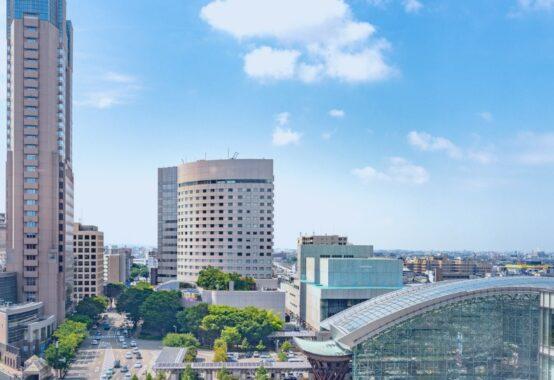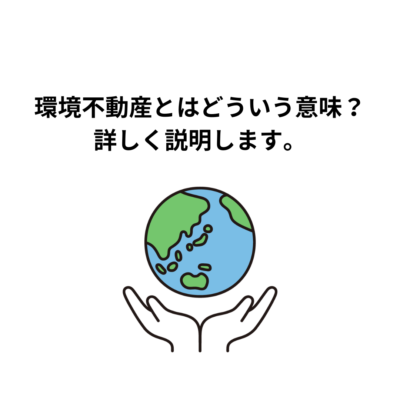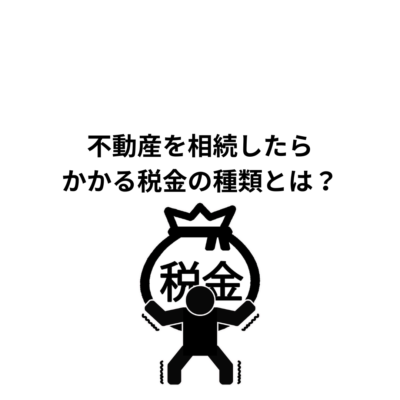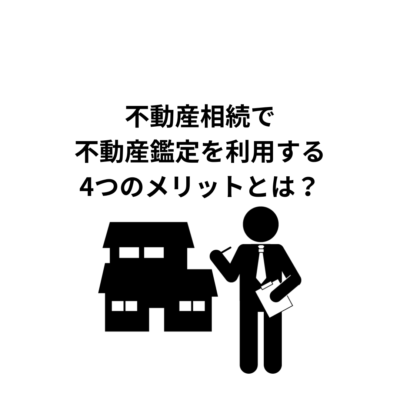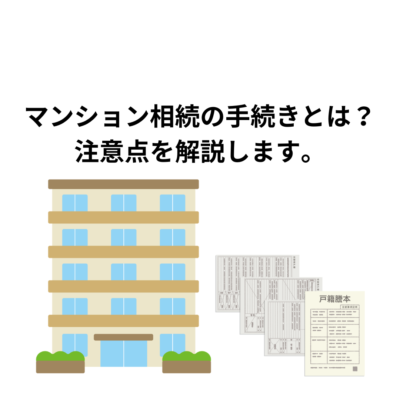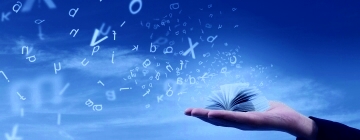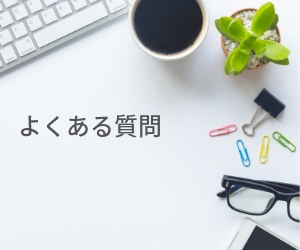大切な家族が亡くなった後、不動産を相続することになったものの、「何から手をつければいいのかわからない…」と悩んでいませんか?
2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければなりません。これを怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。とはいえ、「相続登記は専門家に頼まなければできない」と思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、不動産相続の手続きは自分で行うことも可能です。
自分で手続きを進めることで、費用を抑えることもできますので、本記事をぜひ参考にしてください。
不動産相続登記とは?
不動産相続登記とは、相続により取得した不動産の所有権を登記簿上で正式に変更する手続きのことを指します。この手続きを行うことで、不動産の所有者としての権利が法的に認められることができます。不動産相続の手続きを自分で進めたいと考える方にとっては、登記は最も重要な項目の一つです。
2024年4月1日に不動産相続登記が法律で義務化されました。この法改正は、相続登記が放置されることにより所有者不明土地が増加している現状を改善することを目的としています。
義務化により、相続を知った日から3年以内に登記を行わない場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。このような背景のもと、早めの手続きが重要となっています。
相続登記が義務化されたため、法務局のホームページでは登記手続きについて詳しく説明したハンドブックを公開しております。
相続登記が必要なケースと不要なケース
不動産相続登記が必要となるのは、不動産を相続したり遺贈によって取得した場合です。例えば、住宅や土地を所有していた被相続人が亡くなり、その不動産を相続人が引き継ぐ場合、登記を行う必要があります。これには法定相続分による相続、遺産分割協議を経た相続、遺贈の場合の所有権移転などが含まれます。
一方で、遺産分割協議が未完了で、不動産の所有者を誰にするか決めていない場合などには、まだ登記を行う必要はありません。しかし、協議が成立した時点で速やかに登記を行うことが望ましいです。登記を行わないままでいると、後の相続人間で権利を巡るトラブルが発生する恐れもあります。
不動産の相続手続きを自分で行うための準備
必要書類の一覧と用意のポイント
不動産の相続手続を自分で行うためには、いくつかの必要書類を事前に用意することが重要です。主な書類として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍、相続人全員の印鑑証明書、住民票の写しなどが挙げられます。また、不動産に関する情報を示す登記簿謄本や固定資産評価証明書も必要です。
ポイントは、被相続人の戸籍関係書類を漏れなく収集することです。出生から死亡までの経過が分からない場合、相続人を確定する作業が進まなくなるため、取りこぼしがないように注意しましょう。また、印鑑証明書や住民票の発行には有効期間があるため、最新のものを準備する必要があります。
➤失敗しない不動産相続の手続きの流れとは?必要書類や注意点を解説!
相続人の調査方法と遺産分割協議の重要性
相続登記を進める際には、まず相続人を確定することが必要です。
被相続人の戸籍謄本を基に、すべての法定相続人を確認することで調査を進めます。法定相続人には配偶者や子どもが含まれる場合が多いですが、場合によっては兄弟姉妹など親族が含まれることもあります。
次に、遺産分割協議が重要になります。法定相続分に基づいて共有名義とする方法もありますが、具体的な財産分割について全員の合意が取れる場合には、遺産分割協議書を作成します。この協議書には相続人全員の署名と実印を伴う押印が必要です。遺産分割協議書がないと、相続人間でトラブルが発生しやすくなるため、入念に作成することを心がけましょう。
不動産の特定と登記薄謄本を取得する手順
不動産相続において、まず相続対象となる不動産を特定する必要があります。不動産を特定するためには、不動産所在地や地番、家屋番号を確認します。それに基づき、法務局で登記簿謄本や登記事項証明書を取得します。その人が所有しているすべての不動産が一覧になっている名寄帳(なよせちょう)を取得して不動産に漏れがないか確認しましょう。
登記簿謄本や登記事項証明書を確認することで、被相続人名義の不動産の状況や正確な情報を把握できるようになります。取得手続きの際、誤った情報で申請しないよう、固定資産税納付書や権利証を事前に確認しておくとスムーズです。
戸籍謄本や住民票の収集方法
相続登記を自分で行う際には、被相続人の戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本だけでなく、相続人全員の住民票や印鑑証明書も必要です。戸籍謄本などの書類は、本籍地の市区町村役場で請求できます。郵送での申請も可能ですが、申請書や添付書類に不備がないよう慎重に進めましょう。
住民票や印鑑証明書は、相続人各自が自分の居住地の市区町村役場で発行を依頼します。ほとんどの書類は即日発行されますが、印鑑証明書は印鑑登録が事前に完了している必要があるため、未登録の場合は事前手続きを行いましょう。
相続登記を自分で行うとかかる費用とは
相続登記を自分で行う場合にかかる主な費用には、以下のものがあります。
【証明書の種類と手数料一覧】
戸籍関係の証明書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):450円/通
除籍謄本(除籍全部事項証明書):750円/通
改製原戸籍謄本:750円/通
戸籍の附票の写し:300円/通
住民票・印鑑証明書(※自治体により異なる)
(除)住民票の写し:200~300円/通
印鑑証明書:200~300円/通
固定資産関連の証明書(※自治体により異なる)
固定資産評価証明書:200~400円/通
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記を申請するときに国へ納める税金のことです。
税額は、土地や建物の固定資産税評価額 × 法律で定められた税率 で計算されます。
相続登記の登録免許税
基本税率:1000分の4(0.4%)
例)固定資産税評価額が 1,000万円 の土地 → 登録免許税 4万円
特別税率(遺言による相続人以外の取得):1000分の20(2%)
例)遺言により相続人以外が取得 → 登録免許税 20万円(1,000万円 × 2%)
免税措置について
相続登記を促進するため、一定の要件を満たす場合は 登録免許税が非課税 となる免税措置があります。
詳細は、法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」 のページをご確認ください。
相続登記を自分で行う場合の流れ
ステップ1:相続不動産の調査
相続登記を進めるためには、まず相続の対象となる不動産を正確に特定することが重要です。不動産の所在地や地番、地目、面積などの情報を把握するためには、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得が必要です。これは、法務局の窓口やインターネットを通じて簡単に取得できます。
また、対象不動産が共有名義になっている場合や担保が設定されている場合には、その詳細も確認しておきましょう。この情報は遺産分割協議や手続きの進行において重要になります。不動産相続の手続きを自分で行う場合、最初のステップであるこの調査を丁寧に行うことが成功への鍵です。
ステップ2:遺言書の確認・遺産分割協議書の作成と確認
次に、遺言書が存在する場合、その内容に基づいて相続が行われます。遺言書が無い場合は、法定相続分に基づいて遺産の分割が行われることになります。
相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この協議書に相続人全員の署名押印をしてもらう必要があります。印鑑証明書も添付することで、法務局に手続きを申請する際の信頼性が高まります。
特に、不動産が単独所有の場合や共有物件となる場合、協議の内容を明確にしておかなければ、後々トラブルが発生する可能性があります。
そのため、協議書の内容は慎重に確認し、不明点があれば司法書士など専門家に相談するのも良い方法です。
ステップ3:書類を作成し法務局へ申請
相続不動産の調査や遺産分割協議が完了したら、必要書類を揃えて法務局へ申請します。主な必要書類には、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人の住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産登記申請書などが含まれます。これらの書類が全て揃っていないと申請が受理されませんので注意しましょう。
※戸籍謄本は、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求可となりました。
また、相続登記には登録免許税がかかるため事前に計算しておきましょう。不明点がある場合や不安を感じる場合は、法務局が提供する無料相談サービスを利用すると安心です。不動産相続の手続きを自分で行う際には、誤りや不足がないよう添付書類を再確認してから申請することが大切です。
ステップ4:登記識別情報通知(権利証)の受領
法務局での申請が無事に受理されると、手続きが完了した証明として「登記識別情報通知」が発行されます。これは以前の「権利証」に相当する重要な書類です。新たな所有権を証明するために必要となるため、大切に保管しておきましょう。
この段階で相続登記の一連の手続きは終了します。しかし、手続き後も相続人間で共有となった不動産がある場合や、名義変更した不動産を売却・賃貸する予定がある場合には、その後の管理や連絡を円滑に行う体制を整えておくと安心です。
不動産相続の手続き後に確認すべき内容
不動産相続の手続きが完了した後でも、確認すべき内容があります。まず、法務局から交付される登記識別情報通知(いわゆる権利証)に誤りがないか確認しましょう。また、不動産登記簿に記載された内容が正しいか改めて調査することも大切です。登記簿内容に誤りがある場合、その後の不動産取引や将来的な相続手続きに支障をきたす可能性があります。さらに、不動産の固定資産税の納付先が正しく登録されているかも確認し、必要に応じて自治体に変更申請を行いましょう。
まとめ
不動産相続の手続きを自分で進めることは可能ですが、書類の不備や相続人間の合意形成の難しさから、手続きが滞るケースも少なくありません。特に、被相続人の戸籍を出生から死亡まで揃えることや、遺産分割協議書の作成には慎重な対応が求められます。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、事前に法務局で相談することも有効ですが、専門家に依頼することで、より確実かつスムーズに手続きを進めることができます。
また、不動産相続においては、不動産の適正な評価が求められる場面も多く、不動産鑑定士の意見を取り入れることで、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。
不動産鑑定士を活用するメリットについては、過去の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。